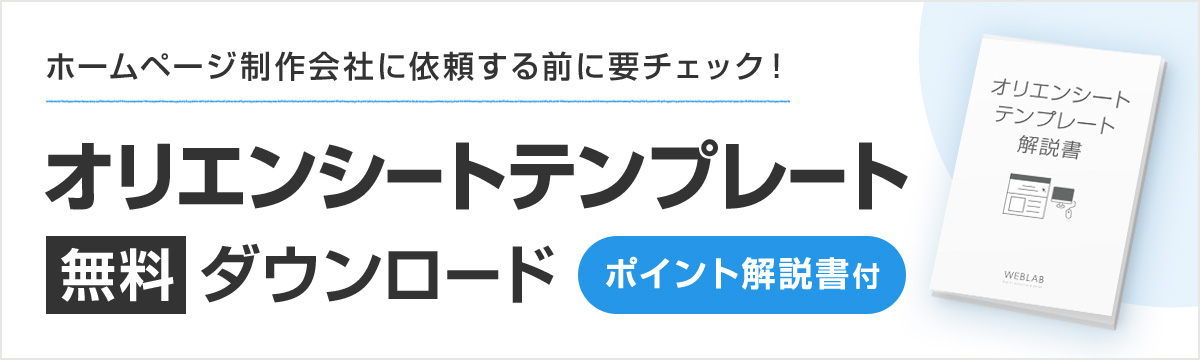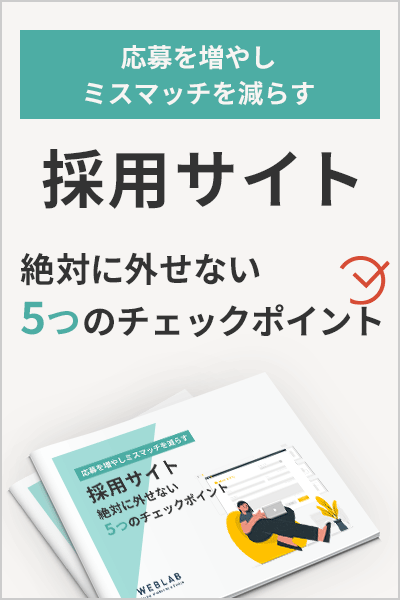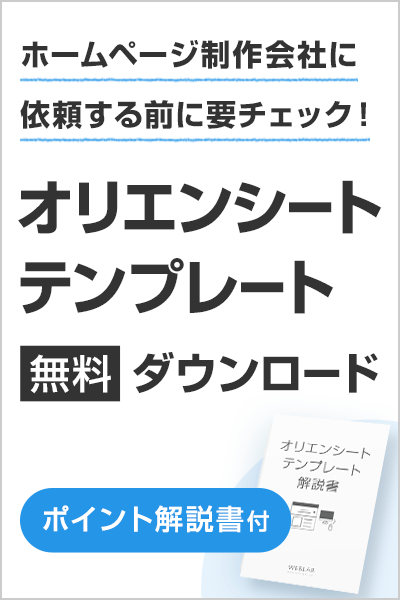サイトリニューアルのスムーズな進め方と成功の秘訣
2025.07.23 Posted by machimura.t

目次
はじめに
「デザインが古い」「スマホで見づらい」「何を優先すべきか分からない」── Webサイトのリニューアルは、ただ見た目を変えるだけの作業ではなく、事業戦略やブランディング、ユーザー体験に直結する重要なプロジェクトです。
とはいえ、どこから手をつけるべきか、何をどこまで社内でやり、どこを制作会社に依頼すべきか、判断に迷う担当者も少なくありません。
この記事では、サイトリニューアルの全体像から具体的な進め方、よくある落とし穴、社内と制作会社の役割分担まで、実務レベルで役立つ情報をわかりやすく整理しました。
サイトリニューアルが必要になる5つの理由

「今のサイト、そろそろ変えたほうがいい気がするけど、理由をうまく説明できない…」
そんなお悩みを抱えているWeb担当者の方は少なくありません。
Webサイトのリニューアルには時間もコストもかかるため、なんとなく進めてしまうと「結局何が変わったのか分からない」「効果が出なかった」となりかねません。
この章では、企業がサイトをリニューアルすべき代表的な5つの理由を、実務視点で詳しく解説します。
理由1:デザインやUIが古く、スマホで見づらい
「なんとなく時代遅れに見える」「スマホだと文字が小さい、レイアウトが崩れる」──
そう感じさせるサイトは、ユーザーの第一印象を大きく損ねてしまいます。
数年前に制作したままのサイトは、デザインのトレンドだけでなく、表示技術やユーザーの閲覧環境も大きく変わっていることが多いです。特に近年では、アクセスの7〜8割がスマートフォンからという業種も少なくなく、モバイルファーストな設計であるかどうかは非常に重要です。
また、ユーザーインターフェース(UI)に問題があると、「問い合わせをしたかったのにボタンが見つからない」「どこから資料をダウンロードできるのかわからない」といった機会損失にもつながります。
理由2:情報が整理されておらず、使いにくい
ページ数が増えていくと、サイト構成が複雑化し、目的の情報にたどり着くのが困難になります。とくに「会社概要」「サービス紹介」「導入事例」などがバラバラに配置されていると、ユーザーは途中で迷子になって離脱してしまいます。
社内で「必要だと思う情報」を都度追加した結果、同じような内容のページが乱立していたり、古い情報が残っていたりするケースも珍しくありません。
「ナビゲーションメニューを見ても、どこに何があるか分からない」「重要な情報が3階層の奥に隠れている」といった構造は、ユーザーにとって大きなストレスになります。
理由3:目的やターゲットが変わった
会社のフェーズや戦略が変わると、Webサイトに求められる役割も変化します。 たとえば、以前は「会社案内」として機能していたサイトが、今は「問い合わせを増やす営業支援ツール」になっていたり、「採用強化のために求職者に訴求したい」サイトになっているかもしれません。
ターゲットが変わったのに、コンテンツや導線が昔のままだと、「自分向けの情報がない」「この会社は古そう」といった誤解を招くことにもなります。
理由4:更新しづらく、情報が古いまま放置されている
「担当者しか更新できない」「CMSが使いにくくて更新を頼みにくい」──
こういった理由で、数か月〜数年も情報が更新されていないサイトは珍しくありません。
情報が古いままだと、ユーザーに「この会社、大丈夫かな?」という不信感を与えたり、掲載されている情報が間違っていて営業機会を逃すこともあります。
また、社内にノウハウが残っておらず、更新のたびに制作会社に依頼して時間とコストがかかっているという課題もよく耳にします。
理由5:SEOやアクセス解析の仕組みが弱い
リニューアル前のサイトでは、Google検索での上位表示が難しい構造になっていることがあります。
たとえば、
- ページのタイトル(titleタグ)や説明文(description)が最適化されていない
- スマホ対応していないためモバイル検索で評価が下がる
- アクセス解析ツールが導入されておらず、どのページが見られているか不明
といった状態では、サイトの効果を最大限発揮することはできません。
PDCAを回して改善を続けるには、現状を分析するための仕組み(Googleアナリティクス、Search Consoleなど)が必要不可欠です。
サイトリニューアルの進め方
Webサイトのリニューアルは、「デザインを新しくするだけ」では済まないプロジェクトです。社内調整、コンテンツ整理、制作会社との連携など、やることは多岐にわたります。この章では、実務に即したかたちで、全体の流れを10ステップに分けてわかりやすく解説します。
ステップ1:現状の課題を把握する
まず最初にすべきは「現状のサイトに、どんな課題があるのか」を洗い出すことです。 たとえば「更新しづらい」「スマホで見づらい」「検索順位が上がらない」など、課題は技術的なものからユーザー体験、社内体制までさまざまです。社内の関係者だけでなく、実際のユーザーやお客様、営業・サポート担当者などにもヒアリングしてみましょう。
アクセス解析(Googleアナリティクス等)も活用すると、感覚ではなくデータに基づいた課題把握ができます。
ポイント:社内の主観とユーザーの声の両方を集めて、課題を客観的に可視化することが成功への第一歩。
ステップ2:リニューアルの目的とKPIを整理する
リニューアルを行う目的は何か、言葉にできますか?
「デザインを刷新したい」「スマホ対応したい」といった目的もありますが、それがどんな成果につながるのかまで突き詰める必要があります。
たとえば「資料請求数を月10件から30件に増やしたい」「自社の採用ページからエントリーを獲得したい」など、具体的な数値目標(KPI)に落とし込むと、プロジェクトの軸がブレにくくなります。
ポイント:KPIを設定することで、社内外の関係者全員が“同じゴール”に向かって動けるようになる。
ステップ3:ターゲットとコンテンツの方向性を定める

Webサイトは誰のためのものでしょうか? 企業の視点だけで考えると、「言いたいこと」ばかりが前面に出たページ構成になってしまいがちです。そうではなく、「誰に見てもらいたいのか」「その人に何を届けるのか」を考え、情報を設計する必要があります。
営業向け、採用向け、既存顧客向けなど、ターゲット別に必要な情報や導線を整理しておくと、リニューアル後の成果につながりやすくなります。
ポイント:1サイト=1ターゲットではなく、“複数ターゲットがどう使うか”を想定してコンテンツを構成する視点が重要。
ステップ4:サイトマップを作成する
次に、サイト全体の構成(サイトマップ)を設計します。
既存ページを見直し、「残す」「統合する」「削除する」を判断しつつ、新たに必要なページを加えていきます。この段階でページ数や構成を確定しておくと、見積やスケジュールも正確に立てやすくなります。
また、各ページの目的(何を伝えたいか、何をしてほしいか)まで定義できると、後の設計やコンテンツ作成もスムーズになります。
ポイント:ページごとの役割を明確にし、「全体のバランス」と「ユーザーの導線」がスムーズになる構成を意識する。
ステップ5:原稿・素材・機能要件を整理する
コンテンツ制作に入る前に、必要な原稿・素材・機能を洗い出します。
たとえば、会社概要や事業紹介、スタッフ紹介など、ページごとにどんな内容が必要か。誰が原稿を用意するのか。写真やイラストはあるか、撮影や購入が必要か。問い合わせフォームや資料ダウンロードなど、どんな機能が必要か。
ここが曖昧なまま制作に入ると、後になって「原稿が足りない」「写真が使えない」「仕様が決まっていない」といったトラブルにつながりがちです。
ポイント:ページ単位で「誰が・いつまでに・何を出すか」を一覧にして、社内の準備状況を見える化しておく。
ステップ6:ワイヤーフレームを作成する

ワイヤーフレームとは「どのページにどんな情報を、どんな順番で配置するか」を視覚化したレイアウト設計図です。
まだデザイン段階ではなく、情報構成に集中します。「一番伝えたい情報はどこに置くか」「どこでアクション(問い合わせなど)を促すか」など、ページの目的に沿った設計が重要です。
ポイント:見た目の美しさよりも、“情報が正しく伝わるか”“導線に無理がないか”を確認することが目的。
ステップ7:デザインを進める
ワイヤーフレームをもとに、ビジュアルデザインの制作に入ります。
配色・写真・フォントなどを使い、ブランドの世界観や信頼感を表現していきます。デザイン案は社内でレビューを行い、必要に応じて修正を加えながらブラッシュアップしていきます。
このとき大切なのは、「かっこいいかどうか」ではなく、「目的に合っているか」「ターゲットに伝わるか」の視点で評価することです。
ポイント:デザインは“見た目”よりも“伝わること”が第一。判断に迷ったら、目的とターゲットを思い出す。
ステップ8:コーディング・CMS構築を進める
デザインが決まったら、それを実際にWeb上で動くページとして組み立てる「コーディング」に入ります。
HTML・CSS・JavaScriptなどを使って、画面に表示されるレイアウトや動きを実装していきます。同時に、スマートフォンやタブレットでも最適に表示されるように「レスポンシブ対応」も行います。
また、更新作業を社内で行うためのCMS(コンテンツ管理システム)の構築もこの段階で行います。CMSがあると、HTMLなどの専門知識がなくても、ページの追加・修正・お知らせ投稿などが簡単にできるようになります。
弊社では、初心者の方でも扱いやすく、機能のカスタマイズにも柔軟に対応できる独自開発CMS「サイト職人CMS」をご提案しています。
ポイント:見た目だけでなく、“更新しやすさ”や“運用のしやすさ”まで含めて作るのが、今どきのWeb制作のスタンダード。
ステップ9:テストを行い、公開の準備をする

公開前には、テスト環境で細かく動作確認を行います。
PC・スマホ・タブレット・各種ブラウザなど、できるだけ多くのパターンで「表示崩れがないか」「リンク切れはないか」「フォームは正しく動くか」などをチェックします。
また、メール通知やサーバーの挙動、本番環境での最終調整もここで実施します。
ポイント:公開前のテストは最終関門。社内チェックリストを活用して、見落としゼロを目指す。
ステップ10:運用と改善を継続する
Webサイトは「作って終わり」ではなく、「作ってからがスタート」です。
Googleアナリティクスやヒートマップツールなどでアクセス状況を確認し、「どこで離脱しているのか」「どのページが人気か」「検索ワードは何か」などを把握しましょう。 その結果をもとに、ページの改善や導線の見直しを繰り返すことで、リニューアルの成果を高めていくことができます。
ポイント:運用担当者・更新フロー・改善サイクルまで含めて、Webサイトは“育てる”ことを前提に設計する。
よくある失敗とその対策
Webサイトのリニューアルでは、計画段階では想定していなかったさまざまなトラブルが起こることがあります。特に中小企業や兼任Web担当者の多い現場では、限られた時間とリソースの中で進行するため、よく似た失敗が繰り返されがちです。
この章では、実際にありがちな5つの失敗と、その回避策をわかりやすく紹介します。
失敗1:社内での合意形成が不十分
リニューアルを進めている途中で「営業部門がこのページに反対している」「経営層がまったく把握していなかった」など、後になって社内から意見が噴出し、方針の見直しを迫られるケースがあります。
これは、初期段階で関係部署や意思決定者の合意を十分に得られていなかったことが原因です。
対策:
- 着手前に、関係する部署(営業・採用・広報・経営層など)からのヒアリングを行い、共通認識をつくる
- リニューアルの目的と優先事項を社内で共有し、「後戻り」を防ぐ土台をつくる
失敗2:スケジュールが楽観的すぎる
「デザインを2週間で決めたい」「来月中には公開したい」といった希望を持つ企業も多いですが、実際には原稿準備や社内確認に時間がかかり、予定より1〜2か月遅れることも珍しくありません。 特に社内での確認フローや決裁プロセスが複雑な場合は、想像以上に時間がかかることがあります。
対策:
- 初期段階で社内調整にかかる時間も含めてスケジュールを立てる
- 社内で「原稿を書く人」「内容を確認する人」「決裁する人」を明確にし、スムーズな進行体制を整える
失敗3:準備不足で制作が止まる

「原稿が出てこない」「写真が揃っていない」「フォームの仕様が決まっていない」といった理由で制作が一時ストップしてしまうこともあります。これによりスケジュールがずれ込み、公開が数週間〜数か月遅延するケースもあります。
対策:
- ページごとに「原稿」「素材」「機能要件」を一覧化し、誰が何を担当するのかを明確にする
- 早めに必要な情報を洗い出し、「あとから気づく」を防ぐ
失敗4:SEOや表示速度への配慮が足りない
「見た目はきれいになったのに、検索順位が下がってアクセスが激減した」というのはよくある失敗例です。画像の重さやタグ構造、リダイレクト設定の不備などが原因です。
対策:
- URLが変更になるページはリダイレクト設定を確実に行う
- meta情報(タイトル・ディスクリプション)の最適化や構造の見直しを設計段階で意識する
- 画像の圧縮やコードの最適化など、ページの表示速度にも配慮する
失敗5:運用体制が整っていない
リニューアル直後はきれいな状態でも、「誰が更新するのか決まっていない」「CMSの使い方がわからない」「情報が古くなっても気づかない」といった状況では、すぐにサイトが放置されてしまいます。
対策:
- 更新担当者・手順・頻度などをあらかじめ決めておき、必要ならマニュアルも整備する
- CMS導入時には操作研修や引き継ぎも実施しておくと安心
リニューアルを成功させるためには、これらの“つまずきやすいポイント”を事前に知っておくことが大切です。第4章では、こうした準備や調整にかかる期間の目安について解説します。
サイトリニューアルにかかる期間はどのくらい?
「リニューアルにはどれくらい時間がかかるのか?」という質問は、多くのWeb担当者が抱える共通の悩みです。実際のところ、かかる期間はサイトの規模や内容、社内体制によって大きく変わってきます。
以下に、代表的な3つのケースに分けて、おおよその目安をご紹介します。
| 規模 | 例 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 小規模 | テンプレート利用サイト、キャンペーンLPなど | 1〜2か月 |
| 中規模 | コーポレートサイト、ECサイトなど | 2〜3か月 |
| 大規模 | 大規模ECサイト、会員制サイト、システム連携が必要なサイトなど | 3〜6か月(1年近くかかることも) |
たとえば、キャンペーン用のランディングページ(LP)や、テンプレートを活用した小規模なサイトであれば、要件が比較的明確なため短期間での公開も可能です。
一方、中規模以上になると、各部署との調整や原稿作成、機能開発など複数の工程が必要となり、時間もそれに比例して延びます。特に大規模な案件では、ステークホルダーが多く関わることで意思決定に時間がかかり、公開まで半年以上を要するケースもあります。
また、実作業よりも社内の準備や確認、素材の収集などに想定以上の時間を要するケースが多いため、「制作期間=プロジェクト全体の期間」とは限りません。あらかじめ余裕を持ったスケジュールを組むことで、トラブルや遅延を防ぎやすくなります。
サイトリニューアル前に確認しておきたいチェックリスト

プロジェクトを始める前に、以下の項目を社内で確認しておくと、リニューアルがスムーズに進み、後からのトラブルも回避しやすくなります。
☐ 現在のサイトにどんな課題があるか、社内で共通認識がある
- 「どこが古いのか」「どこが使いづらいのか」などを具体的に洗い出せているか
- アクセス解析データや顧客の声をもとに課題を把握できているか
☐ リニューアルの目的と、目指す成果(KPI)が定まっている
- 「問い合わせ数を増やしたい」「採用エントリーを増やしたい」など、目的が明確か
- 目標数値(例:月間○件の問い合わせなど)も設定できているか
☐ 主なターゲットとコンテンツの方向性を整理できている
- 誰に向けたサイトか、その人に伝えるべき情報は何か、整理できているか
- 不要なコンテンツが混在していないか
☐ ページ構成(サイトマップ)が大まかに決まっている
- 必要なページ、不要なページの洗い出しはできているか
- 各ページの役割や目的は明確になっているか
☐ 原稿や写真などの準備体制が整っている
- 誰が何の原稿を用意するか、社内で役割分担ができているか
- 撮影・素材調達の予定が立っているか
☐ 社内の確認・決裁フローが整理されている
- 誰が最終決裁をするか、どのタイミングでレビューするか決まっているか
- 複数部署が関わる場合の調整体制があるか
☐ 公開後の運用体制がある程度見えている
- CMSの操作担当や更新フローは誰が担うか、検討できているか
- 更新頻度や改善サイクルについての社内方針があるか
成功のために意識したい3つのポイント
サイトリニューアルは、ただ新しいデザインに変えるだけの作業ではありません。リニューアルの目的を達成し、費用と時間に見合った成果を得るためには、プロジェクト全体を通して意識しておくべきポイントがあります。
この章では、特に重要な3つの観点に絞ってご紹介します。
「社内調整」が最大のボトルネックになりやすい
制作そのものよりも、社内の合意形成や原稿・素材の準備に時間がかかるケースがほとんどです。
たとえば、「誰が最終的に決裁するのかが曖昧」「複数の部署から矛盾する要望が出る」「原稿を頼んだのに何週間も返ってこない」──これらはすべて、プロジェクトの進行を大きく妨げる要因になります。
特に中小企業では、Web担当者が他の業務と兼任していることが多く、想定以上に対応の手が回らないこともあります。
プロジェクトのスタート時点で、社内での決裁フローや確認のタイミング、誰が何を担当するかを明確にしておくことが、円滑な進行のカギになります。
完成度より「運用のしやすさ」を優先する
つい、「完璧な状態で公開したい」と思ってしまいがちですが、リニューアルの本当のスタートは「公開してから」です。
すべてのページを完璧に揃えようとすると、公開が何か月も先延ばしになり、結局タイミングを逃してしまうこともあります。それよりも、まずは必要最低限の状態で公開し、運用しながら育てていく考え方のほうが現実的です。
また、更新しやすいCMSやシンプルな導線を意識しておくことで、リニューアル後の運用負担を大きく減らすことができます。
「後から変更できる」「あとで追加できる」ことを前提に考えると、気持ち的にもスムーズに進みやすくなります。
社外パートナーを“相談相手”として活用する
制作会社や外部パートナーに「丸投げ」するのではなく、「相談相手」「伴走者」として関係を築くことで、より良いリニューアルにつながります。
たとえば、ターゲットや目的に合ったページ構成の提案、競合分析、SEO対策の方向性など、プロの視点からアドバイスをもらうことで、自社だけでは見えなかった視点が得られます。
そのためには、制作会社には自社の現状や課題、目的をしっかり共有することが大切です。単なる発注先ではなく、パートナーとして対話を重ねながらプロジェクトを進めることが、成功への近道です。
以上の3点を意識しておくことで、リニューアルが「見た目を変えるだけ」の作業ではなく、「成果につながるプロジェクト」として進められるようになります。
制作会社を選ぶ際に押さえたいポイント
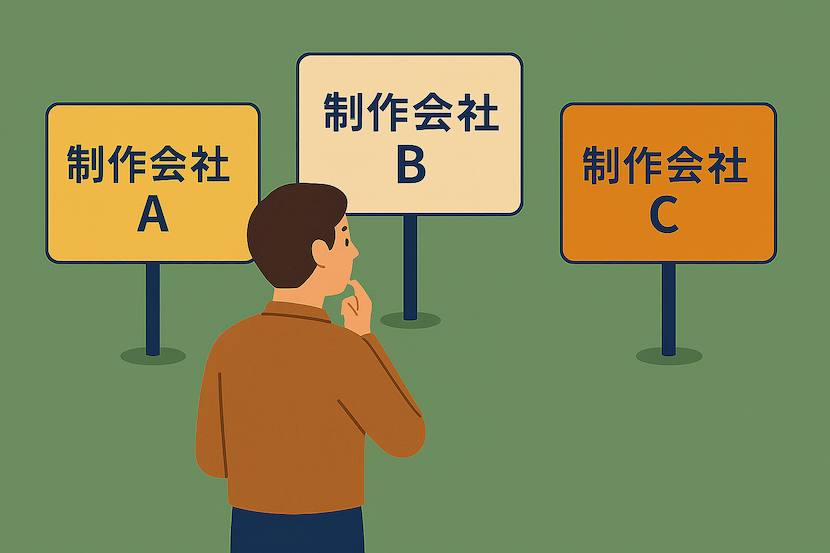
リニューアルを成功させるには、内容だけでなく「誰と一緒に進めるか」も重要な要素です。Web制作会社には、デザイン特化型、開発重視型、マーケティング視点を持つ会社など、それぞれに強みがあります。
自社にとって最適なパートナーを選ぶために、以下のような観点を参考にするとよいでしょう。
課題や目的の整理から相談できるか
成果につながるリニューアルのためには、見た目だけでなく「なぜリニューアルするのか」「誰にどんな価値を伝えたいのか」といった根本的な目的の整理が欠かせません。
そのため、単なる受託ではなく、ヒアリングや提案を通じて、目的や優先順位を一緒に考えてくれるパートナーを選ぶことが大切です。
社内体制やリソースに合わせた柔軟な進行ができるか
会社によっては、専任のWeb担当者がいなかったり、原稿や素材の準備に時間がかかったりと、制作以外の部分でボトルネックが発生することもあります。
そうした社内事情や進め方のクセを理解し、無理のないスケジュールやサポートを提案してくれる制作会社であれば、安心してプロジェクトを進められます。
公開後の運用や改善も見据えているか
サイトは公開して終わりではなく、むしろその後の「運用フェーズ」でこそ成果が見えてきます。
更新のしやすさ、運用サポート、アクセス解析に基づいた改善提案など、「育てる視点」を持った会社かどうかは、長く付き合ううえで非常に重要です。
まとめ
Webサイトのリニューアルは、単なる見た目の刷新ではなく、「事業に貢献する仕組みを作ること」です。
この記事では、リニューアルの必要性から進め方、失敗を防ぐコツ、事前準備や外部パートナー選びのポイントまで、実務視点で幅広くご紹介してきました。
重要なのは、「どこを目指すのか」を明確にし、「社内でできること」「制作会社に任せること」を整理したうえで、無理なく確実にプロジェクトを前に進めることです。
サイトの目的がはっきりすれば、構成やデザイン、機能、運用方針も自然と決まってきます。逆に、そこが曖昧なままだと、どれだけ費用をかけても思うような成果は得られません。
私たちウェブラボでは、目的や課題の整理からご一緒し、公開後の運用・改善までサポートする伴走型のリニューアル支援を得意としています。
「今のサイト、そろそろ変えたほうがいいかな…」と少しでも感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
特定商取引法に基づく表示はどこまで必要?省略できるケースと記載例
2025.11.21
2025.10.09
サステナビリティサイト制作 【完全ガイド|企業価値を高める企画から公開まで】
2025.09.09