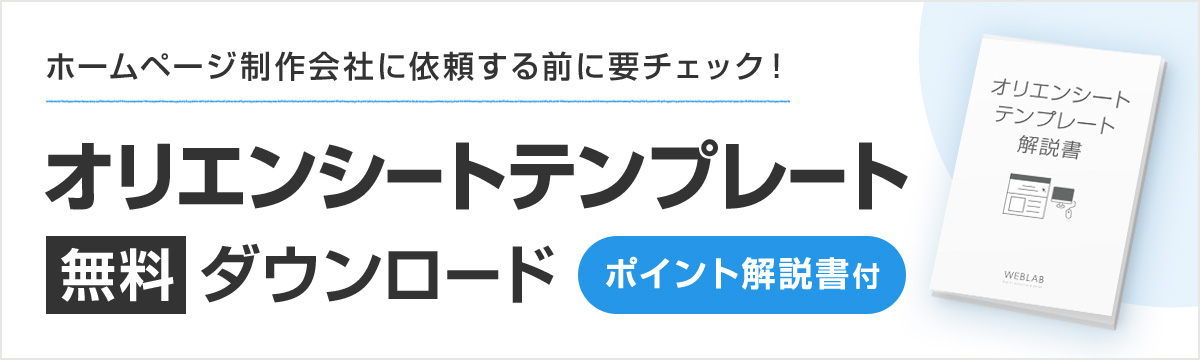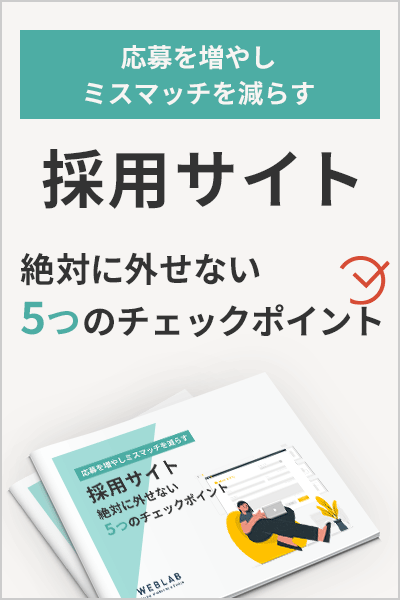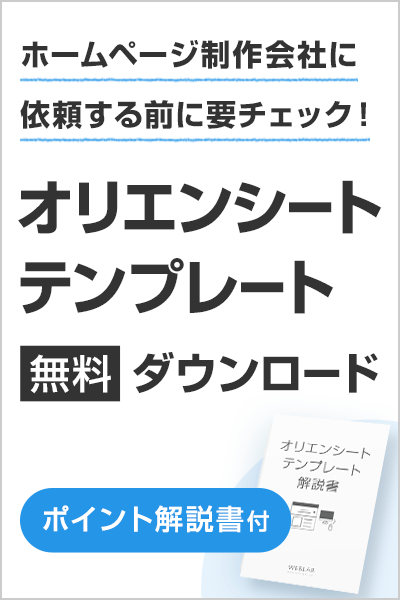サステナビリティサイト制作 【完全ガイド|企業価値を高める企画から公開まで】
2025.09.09 Posted by takahashi.m

サステナビリティへの取り組みは、多くの企業にとって経営の重要課題となっています。投資家や取引先、求職者、消費者など、さまざまなステークホルダーが企業の姿勢を見極める際の基準として注目しているからです。
そうした中で、自社の活動や方針を体系的に伝えるための「サステナビリティサイト」の役割はますます大きくなっています。
本記事では、企画段階で押さえておきたいポイントや、掲載すべき主なコンテンツ、制作から公開までの流れをわかりやすく整理しました。これから制作を進める担当者の方が、一歩を踏み出す際の参考にしていただければ幸いです。
目次
1. なぜ今サステナビリティサイトの制作が必要なのか

企業のサステナビリティ(持続可能性)への取り組みを専用サイトで発信する動きは、大企業に限らず中堅・中小企業にも広がっています。背景には、単なるCSR活動の紹介ではなく、経営戦略の一部として非財務情報を開示する重要性が増していることがあります。
- 投資家はESG(環境・社会・ガバナンス)への対応を重視し、情報が不足している企業は投資対象から外されることもあります。
- 顧客は製品・サービスそのものだけでなく、企業が社会や環境にどう配慮しているかを購買基準にしています。
- 従業員や求職者は「社会的意義のある会社で働きたい」と考えており、方針を明示することが採用や定着につながります。
1.1 企業価値を高める3つの効果
- ブランドと競争力の向上
例:プラスチック削減や再エネ導入などを定量的に開示することで、生活者や取引先から信頼を獲得し、選ばれる理由につながります。 - 人材採用・定着への貢献
例:採用サイトや会社説明会で「女性管理職比率30%を目標にしています」と示すと、学生や若手層に好印象を与えます。 - 新しいビジネス機会とリスク管理
例:サプライチェーンの人権調査を開示したことで、海外取引先との契約が有利に進んだ事例もあります。
1.2 ESG投資・SDGsとの関係
- ESG投資:GPIFをはじめとする機関投資家が重視。企業のESG対応は「投資判断の最初のチェックポイント」になっています。
- SDGs:17の目標のうち、自社がどこに貢献しているのかを明示することで、社会とのつながりを強調できます。
1.3 ステークホルダーとの関係構築の重要性
サステナビリティサイトは、幅広いステークホルダーとの信頼関係を築くための基盤になります。
- 顧客:製品が環境や人権に配慮しているかを示し、購買時の安心感を提供。
- 従業員・求職者:働きがいや多様性への取り組みを発信し、エンゲージメント強化につなげる。
- 投資家:非財務データやリスク管理の方針を明示し、長期的な投資を呼び込む。
- 取引先:調達方針や行動規範を共有し、サプライチェーン全体でリスクを低減。
- 地域社会:地域貢献や環境活動を示し、良き企業市民としての信頼を得る。
つまり、サステナビリティサイトは単なる情報公開にとどまらず、顧客・投資家・従業員・地域社会といった幅広い関係者との信頼関係を築くための場になります。
2. サステナビリティサイト制作で掲載すべき必須コンテンツ

サステナビリティサイトは、「方針 → 取り組み → データ → 成果」 を体系的に示すことが信頼性につながります。以下に具体的な要素を紹介します。
- トップメッセージと方針
企業トップがビジョンやコミットメントを示し、全体の方向性を明確にする。 - ESG(環境・社会・ガバナンス)の取り組み
事業活動に関わる数値や実績をE・S・Gの3領域に整理し、ステークホルダーに理解しやすく伝える。 - マテリアリティ(重要課題)と目標設定
優先課題を特定したプロセスと、課題ごとの数値目標や進捗を開示する。 - ダウンロード資料
詳細なデータや報告書を整理して公開し、投資家や評価機関のニーズに応える。
この4つを揃えることで、サステナビリティサイトは「理念を伝える場」から「企業の信頼性を証明する場」へと進化します。
2.1 トップメッセージと方針
- 代表者の顔写真+直筆サインを添えると責任の所在が伝わりやすい。
- 「理念」だけでなく 具体的な数値目標 を盛り込むと説得力が増す。
例:2030年までにCO₂排出量を2013年比で50%削減。
2.2 ESGの取り組み
ESGとは、サステナビリティに関する情報を整理するときの国際的な基本枠組み(環境=Environment , 社会=Social , ガバナンス=Governance) です。 企業が「どんな方針を持ち、どんな取り組みをしてきたのか」を、数字や実績とあわせて見せることで、投資家をはじめとしたステークホルダーからの信頼を得やすくなります。
ここでは、それぞれの分野でどのような情報を載せるべきかを見ていきましょう。
2.2.1 環境(Environment)に関する情報開示
気候変動や資源の枯渇など、環境課題は今や世界共通の最重要テーマです。 そのため企業には、「自社の事業が環境にどんな影響を与えているのか」「その負荷をどう減らしているのか」を正しく伝える責任があります。
特に、温室効果ガス排出量や気候リスク対応を開示するための国際的な指針 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース) が広く使われており、今やグローバルスタンダードになりつつあります。
| 主な開示内容 | 表現の工夫例 |
|---|---|
|
推移グラフや円グラフで年度ごとの改善を見せる |
2.2.2 社会(Social)に関する情報開示
サステナビリティは環境だけでなく、人や社会との関わりも大きなテーマです。
企業は「従業員が安心して働ける環境を整えているか」「人権を尊重した事業活動をしているか」「地域社会にどう貢献しているか」といった視点で見られています。
多様性の推進(女性管理職比率や障がい者雇用率)、人権デューデリジェンスの実施、従業員の満足度や安全衛生の取り組みなどを数値とともに公開することで、企業の誠実さを示すことができます。
| 主な開示内容 | 表現の工夫例 |
|---|---|
|
インフォグラフィックやアイコンを使い、視覚的に理解しやすくする |
2.2.3 ガバナンス(Governance)に関する情報開示
いくら環境や社会の取り組みを進めていても、経営の意思決定が不透明では信頼を得られません。
そのため、健全で透明性のある経営体制(コーポレート・ガバナンス) を整えていることを示すのが「G」の開示です。
取締役会の構成や独立社外取締役の割合、役員報酬の決め方、内部通報制度の運用状況などを明らかにすることで、不正防止やリスク管理に真剣に取り組んでいることを伝えられます。
| 主な開示内容 | 表現の工夫例 |
|---|---|
|
表形式や組織図で透明性を強調する |
2.3 マテリアリティと目標設定
マテリアリティとは、企業がサステナビリティに取り組む際に「どの課題を最優先に解決すべきか」を整理したものです。
ポイントは、自社にとっての重要性(事業戦略への影響度)と、社会にとっての重要性(ステークホルダーの期待や関心)の両方を踏まえて決めることにあります。
単に「環境に取り組みます」「人を大切にします」と掲げるだけでは説得力がありません。
「どの課題を重要と判断したのか」「その判断はどのようなプロセスを経て行ったのか」を開示することが、説明責任と透明性の確保につながります。
そのうえで、特定した課題ごとに 数値目標(KPI)と進捗 を示すことで、企業の本気度を伝えることができます。
つまり、マテリアリティは「企業の取り組み全体の優先順位表」であり、サイトに掲載することでステークホルダーに対して ロードマップと約束 を見せる役割を果たすのです。
| 項目 | 内容 | 表現の工夫例 |
|---|---|---|
| 特定プロセスの開示 | 課題洗い出し → 影響度評価 → ステークホルダー対話 → 優先順位決定 | フローチャートや図解でプロセスを見せる |
| マテリアリティマトリクス | 事業への影響度 × 社会的影響度を二軸で整理し、優先課題を位置づける | マトリクス図で重要課題を視覚的に提示 |
| 課題ごとの定義と背景 | 「なぜその課題を選んだのか」「社会課題との関連性は何か」を説明 | アイコンや図表を使って直感的に理解できるようにする |
| 数値目標(KPI) | 再エネ比率、労働災害度数率、リサイクル率などの具体的な指標 | 年度ごとの目標・実績を表やグラフで公開 |
| 進捗状況の公開 | 達成度を毎年更新し、改善の有無を明示 | ロードマップや棒グラフで可視化 |
なお、マテリアリティやKPIの裏付けとなる詳細データ(温室効果ガス排出量や従業員データなど)は、「2.4 ダウンロード資料」で提供する形にすると便利です。これにより、サイト上では全体像をわかりやすく示し、詳細は資料から確認できる二段構えの情報設計になります。
2.4 ダウンロード資料
サステナビリティサイトでは、全体像や方針は分かりやすく提示し、より詳細なデータは別途提供する形が理想的です。
特にマテリアリティやKPIの裏付けとなる温室効果ガス排出量の詳細、従業員データ、各種方針文書などは、投資家や評価機関が重視するポイントです。
そのため、サイト上で概要を示しつつ、詳細な情報を PDFやExcel形式でダウンロードできる仕組みを用意すると便利です。
代表的にまとめておきたい資料は以下の通りです。
- 統合報告書(年次の活動を網羅)
- ESGデータブック(環境・社会・ガバナンスの定量データ)
- TCFDレポート(気候関連情報の詳細)
- 各種方針文書(人権方針、環境方針など)
- 外部評価・受賞歴(CDPスコア、ランキングなど)
資料は「年度別」や「カテゴリ別」に整理しておくと、必要な情報を探しやすくなり、透明性の高さも伝わります。
3. サステナビリティサイト制作の進め方(全7ステップ)

サステナビリティサイトは、一般的なコーポレートサイトよりも「情報の正確性」「透明性」「継続的な更新」が求められます。
そのため、場当たり的な進行ではなく、戦略に基づいたステップを踏むことが不可欠です。ここでは、企画から公開、運用までの流れを7つのステップで紹介します。
3.1 ステップ1:目的とターゲットを確認する
- 目的例:投資家への情報開示強化、採用ブランディング、顧客との信頼構築など
- ターゲット例:投資家、顧客、従業員、取引先、地域社会
「誰に」「何を伝えるのか」を定めることが成功の出発点です。
3.2 ステップ2:コンテンツ企画と情報収集
- 経営企画、IR、広報、人事など社内横断で協力体制を構築
- トップメッセージ、ESGの取り組み、マテリアリティなどの素材を集める
- ベンチマーク(他社分析)やストーリーテリングを意識して企画
情報の“素材集め”を丁寧に行うことで、後工程がスムーズになります。
3.3 ステップ3:サイト構造を設計する
- サイトマップを作成し、情報の流れを整理
- 「グローバルナビゲーション(例:サステナビリティトップ/方針/ESG/マテリアリティ/データ・報告書)」を設計
- ユーザーが迷わず欲しい情報にたどり着ける導線を確保
情報設計(IA)は“骨組みづくり”。ここで全体像を固めると後戻りを防げます。
3.4 ステップ4:デザインとワイヤーフレーム作成
- ワイヤーフレーム=Webページの設計図を作成
- デザインでは「誠実さ・透明性・信頼性」を表現
- アクセシビリティ対応(コントラスト比、代替テキストなど)を組み込む
UI/UXの工夫が、ステークホルダーからの「読みやすさ・信頼感」に直結します。
3.5 ステップ5:コーディングとシステム開発
- HTML/CSS/JavaScriptでフロントエンドを構築
- CMS導入で「非エンジニアでも更新できる仕組み」を整備
- 多言語対応、検索機能、レポートDL機能など必要要件を組み込む
サステナビリティサイトは更新頻度が高いため、運用しやすい仕組みづくりが重要です。
3.6 ステップ6:コンテンツ入稿と最終チェック
- 原稿・画像・PDFをCMSに登録
- 誤字脱字や数値のファクトチェックを徹底
- マルチデバイス(PC・スマホ)表示確認、ブラウザ検証も実施
信頼性を担保するため、公開前の「品質保証(QA)」は必須です。
3.7 ステップ7:公開と運用計画
- 公開後はアクセス解析やSearch Consoleを設定
- 更新体制(誰が・いつ・何を更新するか)を明確化
- 効果測定(KPI達成度)→ 改善 → 新規企画のPDCAを継続
公開はゴールではなくスタート。継続的な更新が「信頼の積み重ね」につながります。
この7ステップを踏むことで、「理念を伝えるだけのサイト」ではなく、成果につながるサステナビリティサイトを構築できます。
4. 制作会社の選び方

サステナビリティサイトの制作は、一般的なコーポレートサイト以上に専門知識や整理力が求められます。だからこそ依頼先の制作会社選びは、プロジェクト全体の成果を左右する重要なポイントです。
4.1 専門知識と実績を確認する
- 国際基準への理解:GRIスタンダード、TCFD、SDGsなどの枠組みを知っているか
- 制作実績:IRサイトやサステナビリティサイトを実際に手掛けたことがあるか
- 内容面への関与度:デザインだけでなく、情報整理やコンテンツ企画から関わった実績があるか
提案時に、過去事例を見せてもらい「どのフェーズまでサポートしたか」を確認すると違いがはっきりします。
4.2 提案力とコミュニケーション力
単に依頼内容を形にするだけではなく、改善提案をしてくれるかが重要です。 例えば:
- 「マテリアリティを先に打ち出した方が投資家に伝わりやすいのでは?」
- 「採用ブランディングを狙うなら、社員の声を動画で入れるのがおすすめです」
といった、具体的な“+α”の提案があるかどうか。
また、専門用語を分かりやすく説明できるか、やり取りのレスポンスが早いかなど、プロジェクトを円滑に進める上での“相性”も見ておくべきポイントです。
4.3 公開後の運用サポート
サステナビリティサイトは、公開して終わりではなく定期的に更新し続けることが前提です。そこで以下の点を確認しましょう。
- 更新対応:レポートや活動報告を追加する際に、自社で更新できるか/制作会社に依頼するのか
- 料金体系:更新作業の費用や納期が明確か
- 保守体制:サーバー監視、セキュリティアップデート、バックアップ対応があるか
- 改善提案:アクセス解析やKPIを踏まえた定期的な改善提案があるか
運用を長期的に支えてくれるかどうかは、最初の契約段階で必ずチェックしておきたいところです。
4.4 制作会社を選ぶ際のチェックポイント
- 知識・実績の有無
- 改善提案の姿勢
- 運用サポート体制
この3点を比較基準にすると、自社に合うパートナーを選びやすくなります。
5. サステナビリティサイト制作にかかる期間と進め方の目安

サステナビリティサイトの制作は、情報収集・承認プロセス・運用体制の設計に時間がかかりやすいのが特徴です。制作会社とのやり取りよりも、社内調整の段階で想定以上に時間を要するケースが多いため、計画時点で余裕を持ったスケジュール設計が欠かせません。
5.1 期間を左右する主な要因
- 情報収集の規模
ESGデータやマテリアリティ特定のプロセスなど、関係部署が多岐にわたるほど時間がかかります。 - 社内承認フロー
トップメッセージや方針は役員・広報・法務など複数の確認が必要となり、調整が長引くケースが目立ちます。 - コンテンツ制作の深度
既存資料を再編集するだけなら早く進みますが、取材・撮影・図解を伴う場合は制作工数が大幅に増えます。 - デザイン・システム要件
テンプレート利用かオリジナル設計か、レポート検索や多言語対応を組み込むかによって開発工程が変わります。
5.2 規模別の目安
- 小規模サイトの場合
既存の資料や報告書を中心にまとめる程度であれば、比較的短期間での公開が可能です。スピード重視で最低限の情報を整えたい場合に向いています。 - 中規模サイトの場合
オリジナルデザインや体系立ったコンテンツ設計を行う場合は、数か月単位を想定すると現実的です。部署をまたぐ調整が増えるため、承認フローを早めに固めておくとスムーズに進みます。 - 大規模サイトの場合
多言語対応やデータベース連携、複雑な検索機能などを盛り込むケースでは、半年以上を見込む必要があります。専門知識を持つメンバーや外部パートナーを含めた体制づくりが重要です。
5.3 進め方のポイント
- 初期段階で承認プロセスを可視化する
誰が最終決裁者なのかを明確にし、承認段階をあらかじめ把握しておくと手戻りを防げます。 - 情報整理とデザイン検討を並行させる
内容が固まるのを待つのではなく、集まった情報を順次ワイヤーフレームに反映することで効率的に進められます。 - 運用を見越した体制づくり
公開後に更新が滞ると信頼性が下がります。誰が更新するかを事前に決めて、持続的なサイト運用に備えることが重要です。
6. 参考になる国内企業のサステナビリティサイト事例
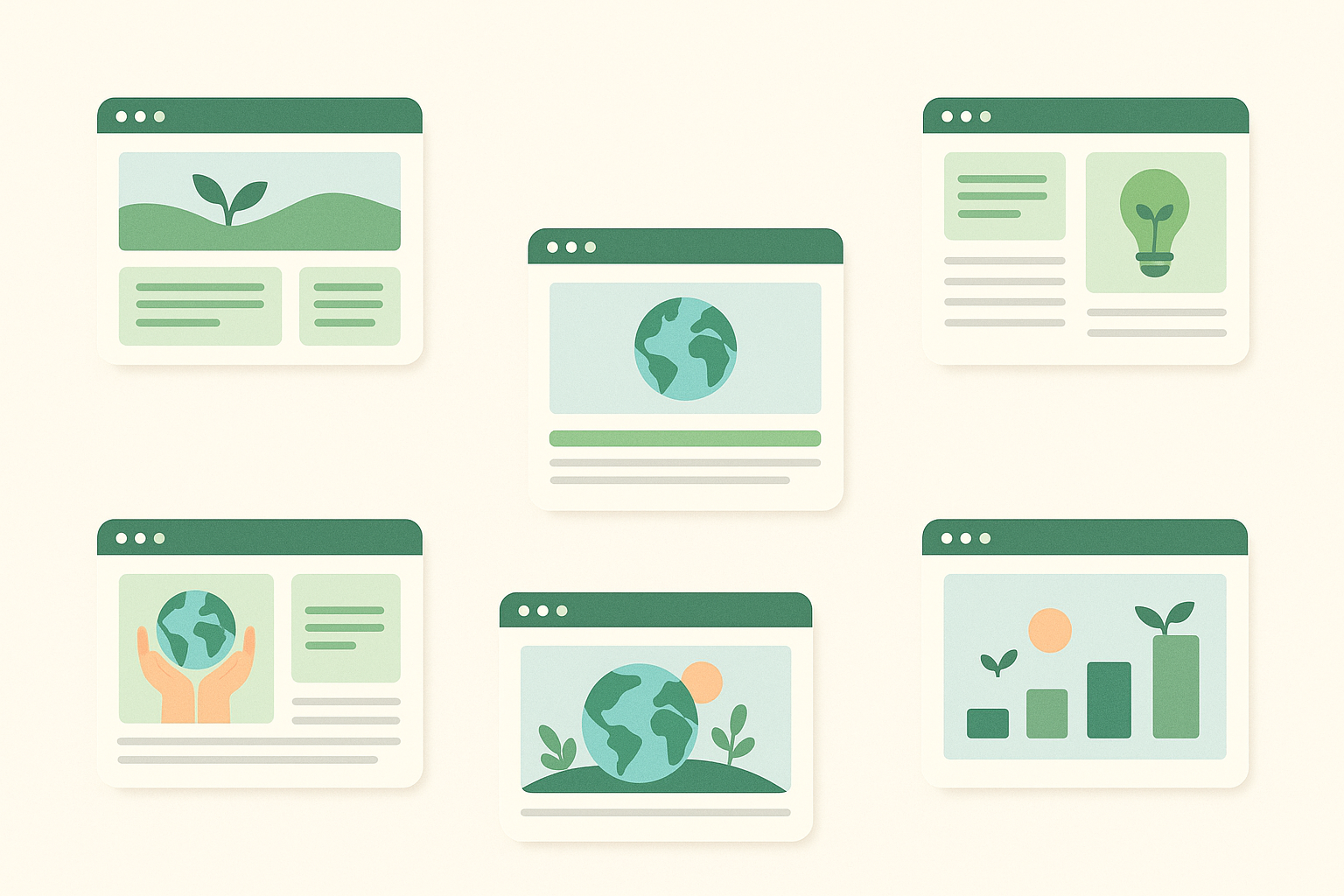
自社のサイトを検討する際、他社の構成や表現を参考にすることは大いに役立ちます。ここでは、特に参考になる国内企業のサステナビリティサイトを紹介します。
| 企業 | デザイン・UI/UX | コンテンツ | 情報構造 |
|---|---|---|---|
| サントリー | 写真や動画を多用し、ストーリー性のあるビジュアル表現 | 水資源・容器リサイクルなど具体テーマをプロジェクトごとに紹介 | 「環境」「人」「社会文化」など直感的なカテゴリ分け |
| NEC | シンプルで堅実。読みやすさと信頼感を重視 | トップメッセージ~ESG施策、詳細データまで網羅 | 社会課題→方針→データの流れが明快。データブックも完備/td> |
| KDDI | 余白を活かしたシンプルデザイン。視認性が高い | マテリアリティとESG施策を体系的に整理 | 「マテリアリティ」「ESG」「レポート」構造で検索性 |
| 住友林業 | 木や自然を想起させる色使い。落ち着いた印象 | 森林・木材資源に関する独自性のある取り組み | 事業とサステナビリティをテーマごとに紐付け |
| 日清食品 | 明るくポップな雰囲気。親しみやすさが強い | 食・健康・環境など生活者に近いテーマを紹介 | 「アクション事例」を切り口にストーリー化 |
6.1 サントリー

“水と生きる”を企業理念に、環境・人・社会文化の幅広い取り組みをストーリー形式で発信。写真やビジュアルの使い方が豊かで、感覚的に伝わりやすいのが特徴です。特に「水資源」や「容器リサイクル」といったテーマごとに、具体的なプロジェクトや成果をわかりやすく整理しており、一般の生活者にも届きやすい表現になっています。
6.2 NEC(日本電気)

「誰もが能力を発揮できる社会を共創する」というパーパスを前面に押し出し、社会課題解決とテクノロジーの関係を明快に提示。トップメッセージから施策、データブックへの導線まで一貫した構造で、投資家や専門機関が必要とする非財務情報が充実しています。社員や社会との関わりを示す事例も多く、読み応えがあります。
6.3 KDDI

「マテリアリティ」「ESGの取り組み」「レポート・データ」といった分かりやすい構成で、求める情報に素早くたどり着ける設計が秀逸です。特に情報開示を体系的に整理しているため、参考資料の探しやすさが際立ちます。シンプルながらも視認性が高いUIで、利用者のストレスを軽減しています。
6.4 住友林業

「森林・木材」という事業の中核をサステナビリティと自然に結び付けた構成。森林資源や住宅事業をテーマにしたコンテンツは、企業の特色を活かしながら持続可能性を語る好例です。ビジュアルも木や自然を想起させる色調でまとめられ、事業との一体感を生んでいます。
6.5 日清食品グループ

「食を通じて社会に貢献する」というブランドメッセージを軸に、プラスチック削減や災害支援といった具体的アクションを紹介。未来志向のプロジェクトも積極的に発信しており、一般消費者から投資家まで幅広い層に届きやすい構成になっています。インフォグラフィックや写真を多用しており、読みやすく親しみやすいデザインが特徴です。
7. まとめ

サステナビリティサイトは、単なる情報発信の場ではなく、企業の姿勢を示す大切な基盤です。投資家や顧客、従業員など、多様なステークホルダーが注目している今こそ、整備を進める意義があります。
記事全体を通じてのポイントを整理すると、以下の通りです。
- 目的とターゲットを明確にする
何のために、誰に向けて情報を発信するのかを最初に決めることで、迷いのない構成ができます。 - 必須コンテンツを揃える
トップメッセージ、マテリアリティ、ESGの取り組み、データ・レポートの整理といった基本要素は外せません。 - 計画的に進める
部署をまたいだ情報収集や承認に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール設計が重要です。 - 運用を見据える
公開後も継続的に更新することで信頼性が高まり、長期的な企業価値の向上につながります。
サステナビリティサイトは、一度作って終わりではなく、継続的に磨き上げる「企業と社会の対話の場」です。今回ご紹介したポイントを参考に、自社に最適な形を検討してみてください。
関連記事こちらの記事も合わせてどうぞ。
特定商取引法に基づく表示はどこまで必要?省略できるケースと記載例
2025.11.21
2025.10.09
ショート動画でSEOを加速!サイトに埋め込むべき理由と具体的な効果
2025.08.08